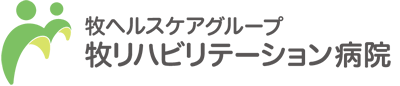医療安全管理指針
-
基本的な考え方
患者さんに安心・安全な医療を提供できるよう、個人レベルのみならず病院全体で組織的な安全管理体制を整えます。
病院長のリーダーシップのもと、全職員で積極的に医療安全に取り組むよう努めます。 -
医療安全管理のための組織体制について
病院長をはじめ、各部署の責任者で構成する医療安全管理委員会を設置し、医療安全に係る責任体制の確立、組織的活動方針及び手順の作成、組織的な教育・訓練の実施、インシデント・アクシデント発生時は当事者等から報告を受け原因分析を行います。 また、各部署にリスクマネジメント委員を置き、現場の医療安全に係る実践と評価を行います。
-
医療安全のための職員の研修・教育について
医療安全管理に関する全職員対象の研修を年2回以上行います。集合研修に参加できない職員に対しては集合研修と同じ知識・技術が習得できるようリスクマネジメント委員が教育を行います。
-
医療に係る安全確保を目的とした改善方策について
広く医療安全に関わる情報を集め、当院のマニュアルを評価します。インシデント・アクシデント事例が発生した際は報告事例の分析を行い、再発防止に努めます。また、再発防止を目的として、組織全体に周知を図り、情報を共有します。各部門は院内の事故防止マニュアルに沿って役割に応じたマニュアルを作成し実践します。
-
医療事故発生時の対応について
医療事故が発生した場合は、「事故発生時の対応マニュアル」に基づき、誠実に対応いたします。 また、人命救助と被害の拡大防止に全力を尽くします。患者さんが死亡するなど重大な事故が発生した場合、医療事故調査・支援センターへ報告し、外部の医療の専門家の支援を受けながら、速やかに院内事故調査を行います。
-
医療安全管理指針の共有について
本指針の内容は、全職員が常時閲覧できるよう各部署に配置するとともに、当院ホームページでも公開し、患者さんおよびご家族がいつでも閲覧できるようにしております。
-
患者さん・ご家族からの相談への対応について
患者さん・ご家族からの病状や治療方針に関する相談に対しては地域連携室が窓口となり、誠実に対応いたします。また、インシデント・アクシデント等医療安全に関する相談には所属長、医療安全管理者が対応いたします。
令和5年9月1日
社会医療法人 ONE FLAG
牧リハビリテーション病院
医療安全管理委員会
感染管理指針
-
基本的な考え方
当院は患者さんの安全を最優先とする感染管理対策を行い、医療関連感染の予防・再発防止を徹底します。
全職員は医療関連感染の防止の重要性を認識し、感染管理ガイドラインを遵守し、より安全で質の高い医療環境の提供に努めます。 -
感染管理のための組織体制
病院長は積極的に医療関連感染管理対策に関わり、感染管理委員会、及びその下部組織として感染対策チームを設置します。
1)感染管理委員会(infection control committee:ICC) 病院長及び医局、看護部、リハビリテーション部、薬剤科、栄養科、放射線科、事務部の各部署責任者、代表者で構成されます。医療関連感染管理の病院全体に関わる方針を決定し、感染対策の業務を推進します。
2)感染対策チーム(infection control team:ICT) ICCの下部組織であり、医局、看護部、リハビリテーション部、薬剤科、栄養科、放射線科、事務部の各部署から選出されたメンバーで構成されます。医療関連感染対策の実務を担当し、医療関連感染に関する監視を行い、情報を収集し、指導・教育する役割を担います。 -
感染管理のための職員の研修・教育
ICTは年2回以上、全職員を対象として医療関連感染管理の研修会を行います。また必要に応じて臨時の研修を開催します。また、院外の研修情報を告知し、参加支援を行います。
-
医療関連感染管理における、職員の基本的な対応
職員は、全部署配布の感染管理委員会ファイル及び、感染管理ガイドラインに従って、医療関連感染防止対策を実施するとともに、自身の体調管理に努めます。
-
感染症の発生状況の報告
当院入院時点ですでに何らかの感染が判明している場合や、院内で感染症に罹患した場合、主治医が感染発生報告を行います。
ICTメンバーは感染情報レポートを定期的に記載します。また各部署責任者は職員の感染症罹患を把握し、患者接触の状況に合わせて関連部署に公表します。 -
医療関連感染の発生時の対応
職員は、医療関連感染を疑われる事例が発生した場合は速やかに感染管理委員会に報告し、感染管理委員会は詳細の把握に努め、必要な場合は専門家の支援も受けながら対策に介入します。
またアウトブレイクが疑われる異常発生時は、迅速に臨時感染管理委員会を開き対応を行います。また、報告の義務付けられている疾患が特定された場合は、速やかに保健所に報告します。 -
感染管理指針の閲覧・情報共有
本指針の内容は、全職員が常時閲覧できるよう各部署に配置するとともに、当院ホームページでも公開し、患者さんおよびご家族がいつでも閲覧できるようにしております。
-
患者さん・ご家族からの相談への対応
感染症の病状や治療方針などに関して、患者さん・ご家族からご相談があった場合には、主治医をはじめとして治療に関わる職員全員が誠実に対応いたします。
令和6年11月1日
社会医療法人 ONE FLAG
牧リハビリテーション病院
感染管理委員会
身体的拘束最小化のための指針
-
身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
患者さんの社会復帰を目指すうえで、尊厳を保持しその人らしい生活を送ることができるよう、身体的拘束がもたらす障害や弊害を認識し、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない医療・看護・ケアに努めます。
-
身体的拘束最小化に関する基本方針
緊急やむを得ない場合(切迫性、非代替性、一時性)を除き身体的拘束は行わず、行う場合も人権尊重、倫理的配慮を念頭に置き、他の選択肢の検討、二次的な障害や偶発症の発生に注意します。 身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限のことをいいます。 身体的拘束最小化に取り組む姿勢として、患者さんの行動を理解したケアに努め身体的拘束ではない代替策を検討します。身体的拘束をする場合は必要性や方法、時間などについて定期的に多職種で検討を行い、早期解除に向けて取り組みます。また、身体的拘束以外の対応の実施や落ち着くための薬を使用する際も、障害や弊害に十分注意し取り組みます。
-
身体的拘束最小化のための体制
専任の医師、看護職、セラピストなど入院医療に携わる多職種で構成される委員会を設置します。身体的拘束の実施状況を把握し、全職員に周知し最小化に向けた医療・看護・ケアの検討を行います。指針の定期的な見直しや職員研修を開催します。
-
医療・看護・ケアに携わる職員に対して、身体的拘束最小化のための研修を年1回実施します。
身体的拘束を行う場合の対応緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合、多職種によるカンファレンスで検討し、事前もしくは実施後速やかに患者さん、ご家族へ説明をし同意を得ます。定期的にカンファンレンスを開催し、速やかな身体的拘束解除に努めます。
身体的拘束最小化の指針の共有について本指針は、全職員が常時閲覧できるよう各部署に配置するとともに、当院ホームページでも公開し、患者さんご家族がいつでも閲覧できるようにしております。
その他、身体的拘束最小化の推進のための基本方針全職員が身体的拘束による障害・弊害を認識し、事故発生時の法的責任問題、人員不足、高次脳機能障害、認知機能障害を理由に安易な身体的拘束をしない医療・看護・ケアの提供を目指していきます。
令和7年4月8日
社会医療法人 ONE FLAG
牧リハビリテーション病院
身体的拘束最小化委員会
適切な意思決定支援に関する指針
-
基本方針
当院は、すべての患者が、その人にとって最善の医療・ケアを受けられるように努力する。患者本人の意思決定を支援するために、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(厚生労働省)等の内容を踏まえ、多職種で構成する医療チーム(以下、多職種チーム)は、患者とその家族などに対して適切な説明と対話を行い、本人の意思決定を尊重した最善の医療・ケアを提供することに努める。
-
入院中の治療や退院支援を行う際の意思決定支援
入院中の治療・ケアや退院支援は、Advance Care Planning(以下、ACP)の一環です。
1)認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援
障害や認知症等で自らが意思決定することが困難な場合、「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に、 可能な限り本人の意思を尊重した決定を行う。
2)身寄りがない患者の意思決定支援
以下のような患者も支援対象とする:
① 家族や親類へ連絡がつかない状況にある人
② 家族の支援が得られない人
身寄りがない患者に関する医療・ケアの方針決定プロセスは、本人の判断能力や財力、信頼できる関係者の有無などの状況によって異なるため、介護・福祉サービスや行政の関与などを活用し、患者の意思を尊重しつつ、「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(厚生労働省)を参考にして、その決定を支援する。
-
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定支援
1)患者本人の意思が確認できる場合
① 方針の決定は、患者の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から、患者本人に適切な情報の提供と十分な説明が必要である。そのうえで、患者と多職種チームは、合意形成に向けて十分な話し合いを行う。患者による意思決定を基本とし、多職種チームとして方針の決定を行う。
② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて患者の意思が変化しうるものである。このことから、多職種チームは、適切な時に、適切な情報の提供と説明を行い、その都度患者が自らの意思を示すことができるように、支援を行うことが必要である。心身の変化により、患者が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うことが必要である。
③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度カルテに記載するものとする。
2)身寄りがない患者の意思決定支援
※家族等とは、本人が信頼を寄せ、人生の最終段階の患者を支える存在であるという趣旨であり、法的な意味での親族関係のみを意味せず、より広い範囲の親しい友人も含め複数人存在することも考えられる。① 家族等が患者の意思を確認していた場合や推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者の意向に沿い、患者にとって最善の方針をとることを基本とする。
② 家族等が患者の意思を確認していない場合や推定できない場合には、家族等と十分に話し合い、患者にとって何が最善であるかを検討し、最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③家族等がいない場合及び家族等が意思決定できず判断を多職種チームに委ねる場合には、医療ケアの妥当性・適切性を判断して患者にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度カルテに記載するものとする。
-
当院で患者や家族がDNARを希望された場合の対応
1)DNAR指示 ※注)1 とは
心肺停止の際に、心肺蘇生術(CPR)を実施しないという患者(家族等)の意思に沿って医師が出す 指示(Order)である。
2)DNAR同意書(以下、同意書)に関する方針
多職種チームと患者・家族等と十分な話し合いを経て、患者本人が同意書に必要事項を記載する。患者に判断能力がない場合は、家族が同意書に必要事項を記入する。同意書は「帳票ファイル」「医師」の保存箇所に保管する。
注)1 DNAR指示:Do Not Attempt Resuscitation OrderACPは人生のあらゆる段階で支援することACPと聞くと「終末期医療」や「最終段階」をイメージし、回復期とはかけ離れたイメージがある。しかし、ACPは急性期・回復期・慢性期のあらゆる段階で本人を人として尊重した医療とケアの意思決定を支援する対話のプロセスである。疾病により発症前のような生活に戻ることが難しくなった患者の退院後の生活を考える時、退院後の生活(人生)が心身ともに豊かになるよう、患者の権利・意思決定を支援することは回復期において重要である。疾患や障害により生活スタイルが変化していく中で、自分らしく生活できるよう本人の意思決定支援を行い、生活の再建に向けて地域生活に繋げるように、多職種チームで患者、家族を支援するよう努力する。
【引用・参考文献】
・厚生労働省:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン,2018年3月改定。
・厚生労働省:認知症の人の日常生活・社会生活における意志決定ガイドライン,2018年6月。
・山縣然太郎(研究代表者):身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン,2019年5月。
・三浦久幸:アドバンス・ケア・プランニング支援ガイド 在宅療養の場で呼吸不全を有する患者さんに対応するために,2022年3月。
令和7年5月1日
社会医療法人 ONE FLAG
牧リハビリテーション病院